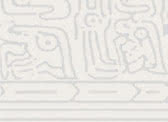阿含経十二因縁釈
第二節 名詞概念の解説
一、名色の意味
色とは地水火風の四大から成る色法を指し、肉眼で見ることができ、例えば色陰である。名とは名法のことで、肉眼では見えないが作用があり、色身に作用し、色身と組み合わさって色陰を形成し、受陰・想陰・行陰・識陰のように覚知され観察される。名色は衆生の五陰身を構成し、衆生が生生世世にわたり実体なき我である。この我は堅固ではなく、壊れ滅びるものであり、生住異滅の法であるため真実の我ではなく、仮に我と名付けられる。名には意根とその作用、六識とその作用が含まれる。
二、縁覚仏と独覚仏
辟支仏には二種類あり、一つは縁覚仏、もう一つは独覚仏である。縁覚仏は仏が住世する時代に生まれ、仏が十二因縁法を説く際にこれに従って修行し、深甚な禅定の中で因縁法を細かに思惟参究し、最終的に辟支仏果を証得する。五蘊世間がすべて因縁によって生じたものであり、一つの縁法が欠けても生じないことを実証する。因縁によって生じた法は空であり、自性がなく無常であることを悟り、この理を証得した者が縁覚仏である。
独覚仏は仏も三宝も住世しない時代に、自ら世間の無常現象を思索し、徐々に十二因縁法に到達し、十二因縁の各支分を実証する。独覚仏は生生世世にわたり仏に従って修行し、善根が非常に深厚である。この世で人界に生まれ仏の住世や弘法に遇わず、仏法も住世しなかったが、前世に修めた善根福德により、世間の一現象を見て心中に疑いが生じ、深い思索を引き起こす。例えば秋風が吹き木の葉が落ちるのを見て疑問を抱き、この現象を明らかにするため深山で独り修行し、生滅の現象を深く参究し続ける。
独覚仏は思索する:人は生まれては死に、木は秋に葉を落とし春にまた生えるのはなぜか。なぜ万物には生滅があるのか。そこで禅定を修めつつ因縁を探求し続け、毎日静坐思惟して万物が生じる根源を求める。これを禅修・思惟修ともいう。長年の苦行を経て十二因縁法を悟り、人無我を証得する。世間の万物万法がすべて因縁によって生じ、因縁所生の法は空・仮・無常であることを知り、辟支仏果を証得する。
独覚仏は四禅八定を得ており、辟支仏果を証得する際、三昧力により神通が現前する。その後は神通で衆生を度す。托鉢に行き衆生が飲食を施せば、その恩に報いるため空中で行住坐臥を示し、体から水を出し体の下から火を出し、山を貫き地に入る。衆生はこれを見て羨み、仏法に信楽を生じてその修行に従う。辟支仏の世間での縁が尽きれば無余涅槃に入り、三界に再来することはない。
阿羅漢と辟支仏は涅槃を証得すると三界を離れるため、仏法は世間に伝わり続けず、苦しむ衆生は救われない。よって仏は二乗の者の慈悲心は薄く、自らの苦を滅するのみで衆生を救うことを考えないと説く。一方、菩薩の慈悲心は大きく、衆生を利楽する全ての事業を放棄せず、慈悲喜捨の四無量心を修め、十の無尽願を発し、生生世世にわたり広く衆生を利し、尽きることがなく、成仏するまで無余涅槃に入らない。成仏後は無数無量の五蘊身を化現して無辺の衆生を利楽する。
三、十二因縁と十因縁における「識」の指すもの
十二因縁において、無明縁行・行縁識・識縁名色の「識」は六識を指す。六識が造る身口意行が後世の業種を残し、入胎して後世の名色が生じる。一方、十因縁の識縁名色・名色縁識における「識」は六識を指さない。名色縁識とは名色がこの識に依存して初めて生住異滅の現象があることを意味し、この識が先にあり、その後名色が生じ六識が現れる。名色には既に六識が含まれるため、六識は名色に従って存在し、生住異滅するものであり、この識に依存して初めて生住異滅が可能となる。よって名色縁識の「識」と六識は同等ではなく、生むものと生まれるものの関係である。この識は天地に先立つ根本識であり、不生不滅で万法を生じる阿頼耶識である。
四、縁起性空の内包
縁起性空は小乗の法空の立場から、如来蔵が生じる一切法がすべて世俗法であると観察するものであり、大乗如来蔵の立場からの観察ではない。世俗の一切法は因縁によって生じ、その形質は空・生滅・壊敗・不永住・不可得・捉えがたいものである。これが小乗の立場から見た世俗法の性質であり、その因は一切法を発起する源であり、過去に造った善悪無記の三業の業種ともいえる。縁は業種が現行して果報となるのを促す人事物の環境である。因縁が具足すれば業果が実現する。因縁所生の法は因縁が変われば法も変わる。よって世間の一切の学問や生業も、絶えず変化する世間の縁に従って変化し、固定不変ではない。
しかし出世間の真理は因縁所生の法ではないため変わらない。もし変われば真理や聖諦とは呼べない。第七識のみが因も縁もなく存在するが、実際には第七識の存在にも因があり、それは第七識の一念の無明である。この一念の無明が滅すれば第七識は滅び存在しなくなる。第七識の存在には縁がなく、無始劫以前から存在し、生起を助ける縁が見つからない。よって第七識には始まりがなく、無明に始まりがないため無始無明と呼ばれる。
一切法が縁起性空であるならば、因も性空で生滅し、縁も性空で生滅する。因縁が滅すれば一切法も滅する。ここには大乗如来蔵法は関わっておらず、如来蔵がこれら一切法を生じたとは述べていないため、小乗の空法と呼ばれる。如来蔵に言及しなければ一切法空は根本点に至らず、あたかも一切法が存在するがゆえに縁起性空であるかのようである。実際、大乗如来蔵の立場から見れば一切法はすべて如来蔵であり、実質的な一切法は存在しない。一切法は生じないため滅することもなく、如来蔵の変相に過ぎない。何が生じ何が滅するというのか。すべて如来蔵の外には出ない。
小乗の空は壊滅的な空であるが、大乗如来蔵の空性は不生不滅の空性心であり、両者の本質は異なり混同してはならない。縁起性空は小乗の空無に過ぎず、大乗如来蔵法の修行内包にはまだ及んでいない。よって縁起性空は不究竟であり、一切世間法の究竟義と本質が何であるかを悟る必要がある。
阿羅漢果や辟支仏果を証得した後、大乗に転じて如来蔵法を修習し、如来蔵を証悟してから漸次に五蘊世間法を観行すれば、五蘊と如来蔵の関係、五蘊が生じ滅する真相が明らかになり、如来蔵の体性と五蘊世間の実質を徹底的に悟り明かし、無明を滅尽して初めて成仏できる。五蘊世間が縁起性空であることを悟るだけでは小乗の空を証得したに過ぎず、成仏はできない。
五、行縁識・識縁名色の正しい理解
まず仏典翻訳において誤解の可能性がある。訳経者の修証レベルは様々で、証量も異なり、証量の全くない訳経者もいるため、翻訳された仏典は法義に差異が生じる。一人が訳せば一つの水準に、複数で訳せば複数の水準になる。かつて小乗行者は意根を理解せず、経典翻訳で意根に関する法義に出会うと理解に偏りが生じ、全く理解できない者もいた。禅定が非常に優れていれば修証でこの不足を補えるが、経典の解説や翻訳ではこの部分の不足を補えず、後世の禅定のない者に様々な誤解を生じさせ、実証できずに推論・分析・憶測に頼らざるを得なくなる。
学仏者が法義を貫通しておらず意根を理解・実証できない場合、経典に対する認識に誤解や不通が生じる。例えば十二因縁の無明縁行・行縁識において、行と識が何を指すか考えても理解できず、両者の関係が整理できず、運行の前後順序が逆転する。もし行縁識の識を第七識や第八識と解釈すれば、法義は大きく誤る。いかなる行が第七識を生じうるのか。第八識の行のみが第七識を生じうるが、第八識には無明がないため無明縁行の部分が説明できない。いかなる行が第八識を生じうるのか。世間・出世間のいかなる行も第八識を生じえない。よって行縁識・識縁名色の識は第七識や第八識ではなく、六識でしかありえない。
ではいかなる行が六識を生じうるのか。ここでの六識は実際には六識の業種を指し、身口意行によって初めて六識の業種が生じる。身口意行と六識は並列関係にあるため、六識は身口意行から生じるのではなく、六識の業種こそが身口意行から生じる。六識は第八識によってのみ生じられ、第七識の無明が助縁となる。第八識は第七識の無明に随順して六識を生じ、身口意行を造作させ、六識の業種を残し、後世に五陰名色が生じる因とする。このように一環一環が連鎖して運行することで、十二因縁の生死輪廻の苦が完結する。
六、諸法因縁生 我説即是空
因は一切法が生じる内的原動力であり、業種とも、過去世に造った業行ともいえる。縁は一切法が生じるために必要な外縁・外力である。業種の因に外の縁が加わって初めて諸法は生じる。しかしその中にはもう一つの理由がある。それは誰が因縁を通じて諸法を生じさせるのかという理由である。この理由は他ならぬ阿頼耶識のみである。
例えば小麦が生じる場合、因は小麦の種子、縁は気候・土壌などである。因縁が具足すれば小麦の芽が生じる。しかし小麦の芽は自ら能動的に生じることはできず、人が種子を土壌に植え、施肥・灌漑・散水・通風が必要である。人がいなければ、小麦の種子と地水火風があっても両者が和合せず、小麦の芽は生じない。
同様に、業種と外の縁だけがあっても、阿頼耶識が両者を統合しなければ諸法は生じない。諸法は七大種子の組み合わせから成り、阿頼耶識にはこの七大種子が含まれ業種も蔵している。外縁外力も諸法の一つであり、同様に七大種子の組み合わせで阿頼耶識から生じる。よって諸法はどのような法であれ、すべて阿頼耶識から生じたものであり、すなわち因縁所生である。
諸法が因縁所生であるならば、本来存在せず後天的に生じたものである。生じれば必ず滅するため、因縁が滅する時、諸法も滅する。よって諸法は空であり、因縁所生の法は空であり、了不可得である。